「維新」は倒幕じゃなかったの?ガソリン減税の先送り、103万円の壁、高校無償化──維新はどこへ向かうのか
維新の名を掲げながら、改革の旗はどこへ消えたのか? ガソリン減税の先送り、103万円の壁の矛盾、そして高校無償化の優先順位。日本維新の会は何を「洗濯」しているのでしょうか?

ガソリン減税反対、103万円の壁は容認
「改革政党」を標榜してきた日本維新の会が、いまやその看板にふさわしい行動を取っているのか、大いに疑問が残ります。たとえば、ガソリン税の減税に反対し、多くの家計を圧迫する要因を先延ばしにしたことは理解しがたい行動です。そして、「103万円の壁」を壊すどころか、むしろ制度の複雑化を容認したことも看過できません。
103万円の壁とは、パートやアルバイトをしている人が一定の収入を超えると扶養から外れてしまい、世帯の手取りが減ってしまう問題です。労働者は収入を抑えざるを得ず、人手不足や経済成長の阻害要因となっています。もっと働きたい人は多いにも関わらず、労働時間を短縮せざるを得ない状況に追い込んでいるのは、明白です。また、その影響で人手不足は悪化し、人員不足による閉店や営業時間の短縮など、売り上げに直結する問題も発生しています。
「維新」の名を掲げる政党
本来ならば、「維新」の名を掲げる政党こそ、時代に合わない壁を取り払い、より自由な働き方を可能にする改革を推進すべきでした。しかし、実際には、高校無償化という比較的低予算で実現可能な政策を優先し、結果として「103万円の壁対策」は後回しにされる形となりました。
本来の103万円の壁を撤去することで、ほぼすべての労働者が減税の効果を実感できたはずが、根本的な解決とはほど遠く、結局は新たな条件や制約という壁が増設されだけの中途半端な内容となりました。
高校無償化はガソリン減税より重要か?
公立高校の授業料はそれほど高額ではなく、既存の支援制度が整っています。私立高校に通う場合でも一定の補助があり、自治体ごとに低所得者向けの支援制度が多数存在します。そのため、所得制限を撤廃することの意義は小さく、また、少ない財源で実現できるということは、実際に困っている人の数が限られていることを示しています。
比較的容易に実現できる「所得制限のない教育無償化」は、低所得者層には恩恵が小さい政策であり、より慎重な議論が求められます。都立高校の授業料は年額11万円ほどですが、年収2000万円の世帯と300万円の世帯では、その負担の重みがまったく異なります。例えば、2000万円の世帯にとっては一人1万円の高級寿司店に行く感覚でも、300万円の世帯では一人1000円の回転寿司が精一杯という状況と同じです。
所得制限があることで不公平が生じるわけではなく、むしろ中間所得層に広く恩恵が行き渡る仕組みの方が公平性の観点から適切ではないでしょうか。
維新と言えば維新志士
「維新」という言葉を聞いたとき、多くの人がまず思い浮かべるのは幕末の志士たちでしょう。坂本龍馬、西郷隆盛、大久保利通、高杉晋作、桂小五郎……彼らは日本の未来を憂い、幕府を倒して新たな時代を築こうと命を賭けて戦いました。
明治維新では、時代遅れの幕藩体制を打破し、日本を近代国家へと押し上げる大改革が行われました。その精神を受け継ぐかのように、日本維新の会も2012年に橋下徹氏を中心に結成され、「維新」という言葉を党名に掲げました。
橋下氏は学生時代から経営コンサルタント大前研一氏の著書『平成維新』に影響を受け、大前氏が1992年に提唱した政治団体「平成維新の会」の理念を強く意識していました。橋下氏は大阪府知事就任直後に大前氏と面会し、「『維新』という名前を使わせてもらえませんか」と直接許可を求め、大前氏は快諾したといいます。その結果、党名「維新の会」は橋下氏が決定したものですが、その背景には大前氏の構想が反映されていると言えます。
橋下氏の現在
橋下氏は都構想の失敗を機に政界を引退し、現在はコメンテーターとしてテレビ出演をしています。かつての改革派の政治家としての姿から一変し、テレビ番組の意向に沿ったコメントをすることで重宝されているように見えます。かつて、記者たちと言い争いをしていた時のような勢いは、もはや感じられません。
そもそも「大阪都」という名称自体が、東京都の二番煎じと感じるような雰囲気もあり、大阪の人々に受け入れられるものではなかったのではないでしょうか。たとえば「大阪国」のような、都を超えるような壮大な名称であれば、より受け入れられやすかった可能性もあったのかもしれません。
日本維新の会はどこに向かうのか?
本来、「維新」という言葉には、「古い体制を刷新し、新しい時代を切り開く」という意味が込められています。しかし、現在の日本維新の会を見ていると、その言葉が単なるキャッチフレーズになってしまっているのではないかと感じることが多いです。
坂本龍馬は「日本を今一度、洗濯いたし申し候」と言いました。これは、腐敗した政治を洗い流し、新しい国家を作り直すという決意の表れです。では、日本維新の会は今、日本の何を「洗濯」しようとしているのでしょうか。
もし、日本維新の会が本当に「維新」の名に恥じない政党でありたいならば、今一度、初心に立ち返り、現状を打破するような大胆な改革を推し進めるべきです。単なる政局の駆け引きではなく、日本全体をより良い方向へ導くような政策を掲げ、実行しなければなりません。
地方分権
また大きな政策として、中央集権型の政治を見直し、地方分権を推進することを掲げ、しがらみのない改革を目指していたはずです。都市部よりも地方の方が車を使う人は多く、ガソリン減税に効果が相対的に大きな影響を持ちます。
既に日本維新の会の政策には、地方分権の理念はほとんど見られなくなっています。かつては道州制など、地方を活性化させるための政策を重要事項としていましたが、現在の維新八策には含まれているものの重点の4項目には入っておらず、選挙時には、地方分権を超え高に掲げているものの、吉村氏が使う言葉で言えば「本気」ではないところに書かれているだけの政策となっているように思えます。
まとめ:今一度、維新の意味を
かつての維新志士たちは、己の立場や損得を超えて、国の未来のために戦いました。西郷隆盛の「命もいらず、名もいらず、官位も金もいらぬ」という一節は、維新志士たちの精神を象徴しています。彼らは自らの利益や名声を求めるのではなく、ただひたすらに国を良くするために戦ったのです。
当初はそのような気概で結党したはずが、時が経つにつれて、その理念が次第に変質してきているように見えます。維新志士が命を懸けて改革を成し遂げたのに対し、現代の「維新」はどこまで本気で日本の形を変えようとしているのでしょうか。維新の名を掲げる以上、彼らはかつての志士たちと同じ気概を持つべきではないでしょうか。
絶好の機会だった?
日本維新の会が本当に「維新」の名にふさわしい政党でありたいのであれば、今こそ原点に立ち返り、大胆な改革を推し進めるべきでしょう。少数与党となったこのタイミングは、独自の大胆な政策を打ち出す絶好の機会であったにもかかわらず、小さな政策で協調することに終始したのは惜しまれるところです。
幕末の志士たちは、自らの利益ではなく、国の未来のために立ち上がりました。維新の名を掲げる以上、現代の「維新」もまた、既存の政治勢力に安住するのではなく、意義のある改革を推し進めることが求められます。地域政党の枠を超え、全国の国民が期待を寄せる政党へと成長するために、今こそ本気で行動を起こす最後の機会かもしれません。
完全ノーリスクのトレード・シミュレーターで自由に練習&検証!
ワンクリックFXトレーニングMAXの詳細ページ



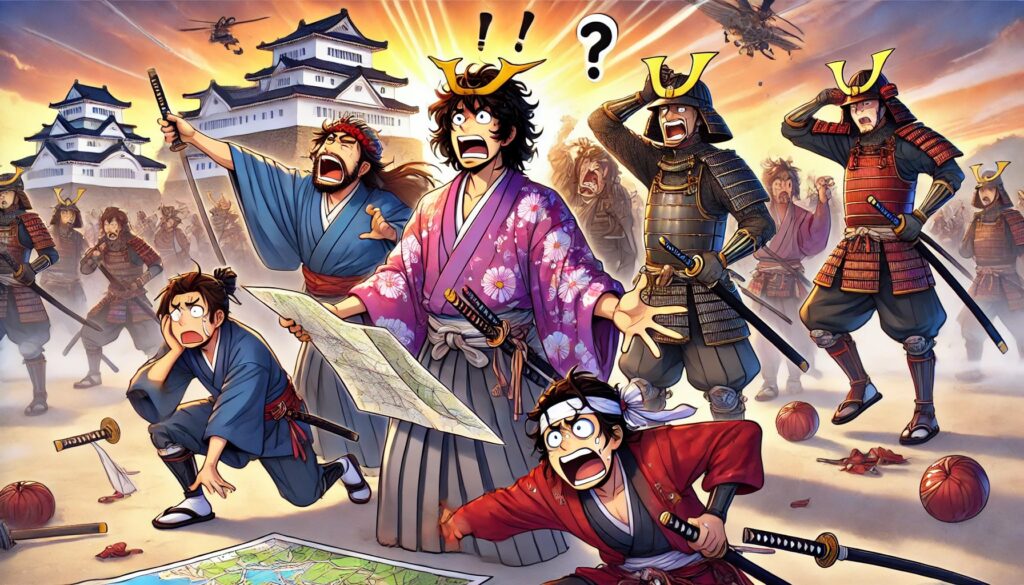

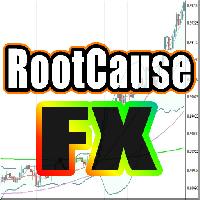
Is it OK?